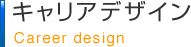
| 日本映画の衰退がいわれて久しいが、長い伝統と固有性とをもった日本文化の基盤は必ずしも失われてはいない。グローバライゼーションは、世界の諸基準や方策、思考を一方的にわが国に移入することではない。起業・創業もまた、グローバル化した地球市場を展望するものでなければならない。今回は、日本文化の美しさの基盤である「耽美」をコンセプトに、映画、美術、ファッション、出版など多彩なシーンにおいて、世界を股にかけたビジネス展開にチャレンジするとともに、日本文化を世界のアート市場に広げるスキームへの若者の参加を熱く呼びかけている高野育郎氏をゲストにお迎えした。 |
(インタビューアー : 高崎経済大学大学院教授 HuSEEC会長 茂木一之)
茂木 高野育郎さんといえば、超高級モード誌『ロフィシェル・ジャポン』、ハイエンド・ソサエティ雑誌『アディクタム』などの編集人兼編集長である一方、美術品の評論・コレクター、高級料理店経営者としてご活躍中ですが、何といっても、2000年の大ヒット映画『バトルロワイアル』のエクゼクティブ・プロデューサーとして知られています。『バトルロワイアル』プロデュースの経緯について教えて下さい。
高野  周りには初打席満塁ホームランと言われているけれど、決してそうではなくその前段階があります。日タイ合作の映画を紆余曲折がありながら完成まで漕ぎつけたのですが、どうもコンセプトが違うと思えたので試写室段階で打ち切りました。また、いくつかの映画制作にも参画しました。
周りには初打席満塁ホームランと言われているけれど、決してそうではなくその前段階があります。日タイ合作の映画を紆余曲折がありながら完成まで漕ぎつけたのですが、どうもコンセプトが違うと思えたので試写室段階で打ち切りました。また、いくつかの映画制作にも参画しました。
そんなことが深作欣二監督の耳に入ったのでしょう。当時、『バトルロワイアル』の映画化を切望されていたものの、資金不足から頓挫していた深作監督が、人づてに依頼してきました。当初はあまり乗り気ではなかったのだが、映画制作・配給会社がこぞって映画化に反対していて、周囲が反対するもの、躊躇するものにこそビジネス・チャンスがあると思い、映画化に乗り出しました。
映画の成功もさることながら、「このご時世にポケット・マネーで映画を作るヤツがいる」という、自分の会社のクレジット・ビジネスをプロモーションできればいいという考えだったわけです。
茂木 第5回日本ホラー小説大賞で残酷だと酷評され、その後の映画でも国会で取り上げるなどの問題作であったが、この小説をどうして映画がされようとしたのですか。
高野 原作に惚れ込んだわけではないのだけれど、原作はあくまでも素材であって、それをどのように魅せることができるか、深作さんの才能に賭けました。
茂木 寺田寅彦は、映画は芸術と科学との結婚によって生まれた麒麟児である、といっています。まさに、映画はモダン・アートなのであり、歴史的芸術の複合体でもあります。そうした意味で、高野さんが追い求める「美」と映画とはどのように関わるのでしょうか。
高野 芸術は、時代の予言者です。綺麗である必要はない。時代の概念が抽出されたもの、それに触れれば時代が向かう方向が分かるものでなければならないでしょうネ。表現が際だっているだけではなく、次の時代がどのような方向に向かっているのかを予言するものが芸術であり、それが「美」につながっていく。もちろん、芸術一般が時代の予言者だとしても、映画芸術には大衆文化という側面が常に付帯しています。
茂木 「光にむかう3つの夢想曲」を監督した西 周成は、「芸術が存続しうる文化は本質的にヒエラルキー的である。だが、そのヒエラルキーは精神的なものであり、世俗的な権威によって与えられるものではあり得ない」、と映画の文化としての総合性と非世俗性を主張しているのですが、高野さんにとって、文化の中で映画はどのような位置にあるのでしょうか。
高野 映画芸術は、時代に迎合するものではないのだけれど、しかし時代に受け入れられなければならないと思う。ビジネスとしての構図を明確にし、どのようにしたら観客動員数を増やすことができるか、など表現とは異なる商業主義的次元の「軸」をもっていなければ映画芸術は完成しないよネ。
茂木 日本の映画づくりも100年の歴史を有していますが、劇場映画の観客動員数は、1960年の約10億人から2000年には1億5千万人と10分の1。興行収入の配分は映画館、配給会社、最後に製作会社の順に行われることになるため、各当事者の収益は興行の成否次第となり、作品が興行的に不評である場合には配給会社、製作会社の投下資金が回収できない事態が起こります。
とりわけ興行収入の配分が後位となる製作者の背負うリスクは大きく、自由な作品づくりが進まない原因にもなっていますが、こうした点についてどのようにお考えですか。
高野 まず、監督は「村」からでなければいけない。「村」には「ムラ」の生活があり、それなりに生きていけるのだけれど、映画に携わる監督にはそれができない。一本作ったら、それで終わってしまうのが悲しい現実ですよ。俺もめったに映画館に行かない。方法論として、DVDがあるから観る側でリッピングしちゃう。今や、映画の演出それ自体をテクノロジーとして考えなくちゃいけなくなってきているのに、興行や制作のあり方がそれについて行けなくなっている。
シネコンがはやっているけど、これだってまだまだだよ。いろいろな仕掛けが考えられるし、箱そのものの複合化・魅力づくりが大切。映画のプロデュースというのは、マルチメディア対応、ネットワーク対応だけではなく、映画館そのもののあり方もその視野に入れていなくてはならない。